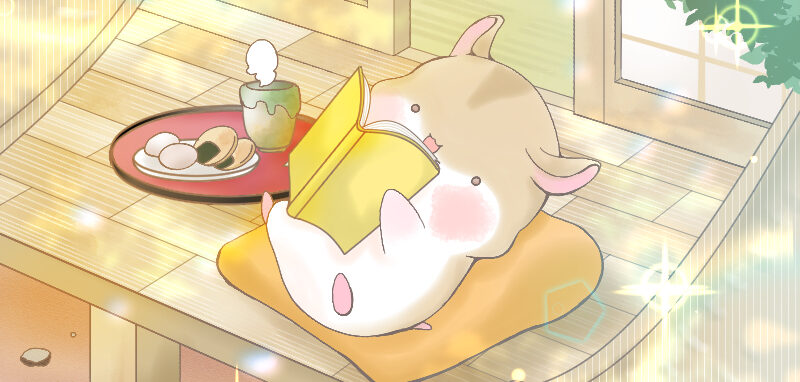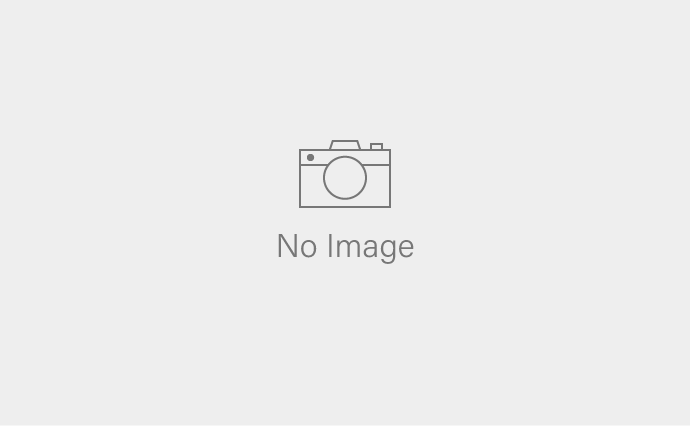こんにちは。ほんのダイアリー管理人の本野まおです。
今回は12月に行った司書補研修会について書いていきます。
今年から長年、司書として勤務されている先生方は私を含めて一人1校の専任になりました。今まで5校兼務だったので大変でしたが、代わりに司書補の方々が雇用されました。
しかし、雇用された方々は司書未経験の方ばかり。
引継ぎだけでは分からない業務(読み聞かせ、選書、ブックトーク、学習支援など)もあるため、夏休みに一度、意見交換会を開き、色々と意見を聞きました。
そして冬休みに入るころには、司書補の先生方も若干、仕事に慣れてきたのではないか?と思い、2回目の意見交換会を立ち上げました。
しかし、ただの意見交換会ではありません。
今回は読み聞かせとブックトークの研修をすることにしました!
研修内容を読み聞かせとブックトークにしたのは何故か?
研修内容も色々悩んだんですが、私が司書としてやっていくうえで、けっこう困ったのが読み聞かせでした。
どんな風によめばいいのか?本の持ち方はどうすればいいのか?どんな本を選んだらいいのか?と、ハテナだらけの中、試行錯誤して読み聞かせを行っていました。
ブックトークも同じ。まずブックトークってなんだ?本の紹介をテーマに沿って行うとはどういうことか?まず何冊ほどするものなのか?テーマって何だ?とこれまたハテナだらけの中、学校司書部会でブックトークの研修があり、そこで基本を教えてもらいました。
また県の図書館講習や研修に参加して、読み聞かせやブックトーク、設営や運営について学んできました。
そういった経験もあり、多分、司書補の先生方が今悩んでいるのは読み聞かせなんじゃないかな?と考えた私は読み聞かせとブックトークを主とした講習を行うことに決めました。
研修の準備
さて、「研修をやりますよ~」と先生方にお知らせする前に、まずは文書作成です。
といっても、司書部会もない今、私がやるのは完全な個人研修なので、案内は簡単にしました。
12月〇日、〇〇図書館センター会議室で読み聞かせとブックトークの研修を行います。時間は9時から16時45分まで。それぞれ、読み聞かせとブックトークを行ってもらうので「冬」に関するテーマで3冊ほど本を持ってきてください。
という文書を作成。
そして、勤務校へ研修を行う旨を伝え、教育委員会に研修案内文書の依頼と、各学校に向けての発送をお願いしました。
※研修は勤務扱いになるので、出勤簿もそのまま印鑑を押します。
ブックトークや読み聞かせについての資料も作成しました。これまた簡潔に作りましたよ。資料はネットや読み聞かせやブックトークの本を参考にして作成しました。
研修会当日の様子
研修会当日は、どことなく緊張した面持ちの司書補の先生方が、それぞれ読み聞かせやブックトークについての本を持ってきました。
今回は初めて会う先生方もいらしたので、軽く自己紹介してから研修スタート!
最初は私がブックトークを行いました。ちなみにテーマは「冬眠」についてです。
にしても、何度も練習していたのに、いざやろうとすると頭の中で軽くパニックを起こす私。なんとかテーマをつなげて行ったものの、うまくできなかったです(>_<)
このとき私はテーマを冬眠にして、絵本、図鑑、読み物の3種類、分類も400(自然科学)600(産業)の本を集めました。そしてなおかつ国語の教科書で紹介されている本を中心にブックトークの流れを構成しました。
司書補の先生方の進め方について
私のブックトークを見た後は、グループを組んで20分ブックトークの内容について話し合う時間を設けました。
時間を設けておかないと、ずるずる時間が過ぎてしまいます。誰が発表するか?どんなテーマでどんな本を紹介するか?を短時間で決めないといけません。
実際に研修を行うとき「発表はちょっと・・・」という理由で不参加の先生もいたり、先生方から発表することに抵抗があることも聞いていましたが、多分、この仕事をしていると遅かれ早かれ、読み聞かせとブックトークは先生方から依頼されると思うのです。
その時に1度でも実演したことがあるかないか、という体験はその後の読み聞かせやブックトークでも活かされるので、ぜひ発表してほしいところです。
その後は各グループの先生方がブックトークの演習。私はテーマや紹介した本を写真に収めたり、使われた本のリストを書き込みます。(後日配布するため)
全部のグループがブックトークについて発表し終えたところで、休憩をはさみます。
読み聞かせの演習
次に読み聞かせの演習も行いました。テーマは「小学校の体験入学に来た子どもたちに向けて」という設定です。
2月になると新一年生が入学予定の小学校に体験入学のため訪れます。
その時に10分ほど読み聞かせを行う学校もあるので、その設定で行いました。
私は「入学」をテーマにした本を読むことが多いのですが、その日は仕掛け絵本をチョイス。(白くまさんのパンツ。知っている方はいますか?)
これも先生方の前で実演。読み聞かせの時に気を付ける事として、本を持つ角度、声の大きさとテンポ、読後感が面白い、いい気持ちの本をなるだけ選ぶということをお話ししました。
私が気を付けていること①
ここで、読み聞かせの時に私が気を付けていることについて書きます。
本を持つときには、しっかりと本に開きグセをつけ、本を広げやすくします。
私は本の下部分をしっかりと固定する形にしています。ページをめくるときには下の端っこから指を入れてページをめくるようにしていますが、ページのめくり方は人それぞれなので、ここでは矯正しません。
ただ、ページをめくるときに本の前を横切る形にしてめくらないように気を付けています。見ている方からすると読み手の手が邪魔になるからです。
また、声も少し大きめに出すように心がけています。特に読み聞かせに不慣れな場合、読んでいるうちに声が小さくなってくることがあります。
前にいる子どもは聞こえても、後ろの子どもは「?」となりかねません。
たまに「声は聞こえていますか?」と声掛けするのも良いですね。
私が気を付けていること②
読み聞かせする本の内容、どんな本が良いか悩みますよね。私も未だに迷います(*_*)
ただ、読み聞かせ会の内容にもよりますが、なるだけ明るい感じで終わるものを選んでいます。
読み聞かせを楽しみにしている子どもたちに、悲しい結末の本や、深く考えさせるような本は控えています。
これが戦争やいじめをテーマにしたもの、または命の大切さについての本であれば上に挙げたような内容の本でも構いませんが、そうでないかぎりは、短めに読み終わる本、聞いている子も参加できるような仕掛け絵本などを選んだ方が、読み聞かせをする方もやりやすいです。
あとは、5冊ほど本を用意して持っていく。これは時間より早く本を読み終わってしまったときに別の本を読むことができるし、こんな本もあるよという紹介もできるので。
司書補の先生方にも演習後に、上記の事をお話ししました。
どうしても自分が読みたい本があるときは、導入の時点でお話してから読み始めるといいですね。
司書補の先生方の感想
そんなこんなで、無事、研修会も終わり、先生方に感想を聞いてみました。
「まずブックトークって何だ?と思いました。そんな言葉も知らなかったし、いきなり先生方から頼まれても無理!今日実践できてよかったと思います」
「読み聞かせはついつい早口になってしまうから、読むときに気を付けます」
「どっちも今日やってみてよかったと思う。これで少しは自信がついた」
など、前向きな感想がもらえてほっとしました。
また「読み聞かせの時間が苦痛なのですが、どうしたらいいですか?」と質問がきたので、まずは「ちゃんと読まなきゃ」という思い込みを解いて、リラックスした気持ちで読むようにすることと、練習を5~10回は行うことを推奨しました。あとは慣れもありますが、自分が楽しんで読むことでしょうか。
練習は自信に直結しますからね。