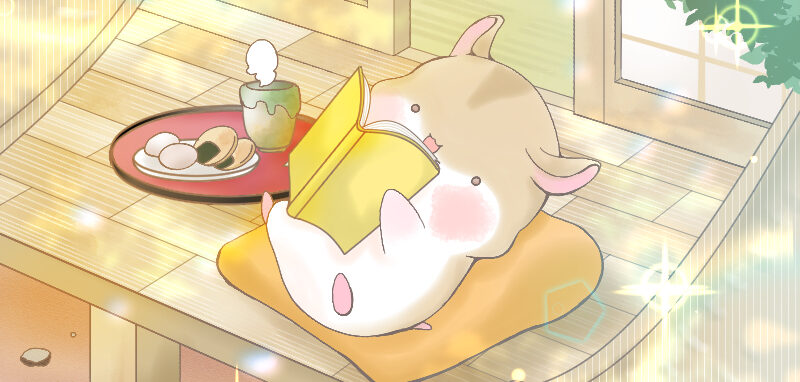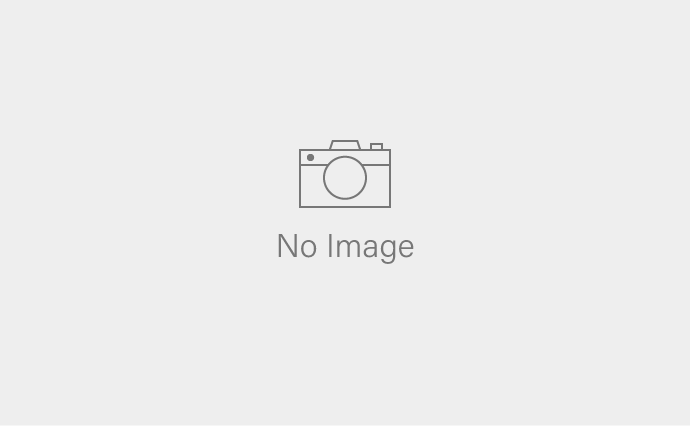こんにちは。ほんのダイアリーの本野まおです。

10月・11月は学校の読書週間や読書月間のイベントをどんなふうにしようか、
悩んだことはありませんか?
私もその中の一人です。
去年やったイベントネタから、子どもたちに評判の良かったものを少しグレードアップして行ったり、種類を増やして行ったりしています。
学校によりけりですが、本当に反応が違うんですよね。A小学校では人気だったイベントがB小学校だとイマイチ・・・。という。
そんな中でも、こんなことやってましたよという息の長い図書イベントをまとめてみました。よければ参考にして取り組んでみてください。
10年間の振り返りを交えてお伝えします。
今までやってきた読書イベントネタ
同じイベントでも毎年違う反応があったり、改良を加えたり色々変えて実践しています。
その① 読書ビンゴ
もう、学校図書館では定番なんじゃないか?と思うほど、どこの学校でも取り組んでいるイベントです。
ビンゴはやりやすい。とにかく自由に設定可能なところがありがたいです。
分類番号ビンゴ、必読書ビンゴ、〇〇テーマのビンゴ、教科書に出てくる本ビンゴ
歴史人物ビンゴ、郷土ビンゴなど色んなビンゴができあがります。
マス目も9マス、16マス、と正方形のものもあれば、12マス、15マスとマスの数にあわせて埋めていくのもあります。
タテ1列そろったら、1冊貸出券をプレゼント!とか、6マスうめたらしおりをプレゼント、というふうに景品もカスタマイズできるし、ビンゴの中身もグレードアップすることも可能です。
私は種類の違うビンゴを4種類ほどんどつくり、全種類制覇した人にはノベルティグッズをあげたりしていました。
エックスで図書館イベント用、配布用のイラストやしおりを載せている方もいます。
ネットでも使えそうなものは、バンバン使って作成しましょう。
その② 読書クイズ
クイズもビンゴと同じようにつくりますが、学校で「おすすめの本の紹介」など、本を紹介するイベントを行っている学校もあると思います。
そこに紹介されている本の中からクイズをつくって、「答えは本の中に!読んでみて」などのシンプルなポップを本の近くに置いていくと、そのまま借りていくことが多いです。
クイズ用紙には「〇ページを調べてみよう」とクイズの答えがあるページを小さく書いておくと、参加する人が分かりやすくて取り組みやすいです。
その③ 読書パズル
こちらは、学年(または各クラス)ごとに目標冊数をきめて、その目標冊数分のイラストを切ったものを用意します。
あとは本を借りたらイラストの破片をもらい、廊下などに掲示してある番号が書いてある用紙と、破片の番号が同じものを貼っていきます。全部貼ることができたらイラストが出来上がります。というもの。
切り分けたりするのが大変ですが、貼っていくうちにイラストができあがってくると完成に向けて本を借りるのも楽しくなってきます。
その④ 巡回読書郵便
これは、私が兼務していたころ実践していました。
当時の司書の先生が、自分の兼務している学校同士で交流学習などを行っていたことをきっかけに、学校で読書郵便を書き上げて自分の勤務している学校で読書郵便で交流したらいいのでは?という思いがきっかけとなり、巡回読書郵便が始まりました。
引継ぎのときに、私が学校同士での交流がない小学校も兼務することになり、このイベントをどうしようか考えましたが、ちょうど各小学校で「おすすめの本の紹介」でおすすめの本をはがきサイズの紙に書いて掲示しているのを見て、
「地区内では先生方との交流もあるし、このさい、自分のまわる全部の小学校の読書郵便を巡回して掲示したらいいんじゃないか?そしたら関わりのない学校同士での読書のつながりみたいなものができるんじゃないか?」
と考えた末、自分の勤務校に回す形態がうまれました。
コロナがはやる前は、地元の中学校の司書さんにお願いして中学校でも掲示させてもらってました。けれどコロナになってからは触れる物も気を付けないといけなくなり、自分の勤務校のみの掲示になりました。
各学校の判断にもよるので、一概にできるか微妙なところはありますが、おおむねどこの小学校でも快く巡回読書郵便を引き受けてくださいました。
もし、兼務されている司書の方がいたときは、ぜひやってみてください。
各小学校ごとで特色がでるんだなぁ、としみじみ思いました。
その⑤ 校内読書郵便
校内読書郵便は、学校内で異学年同士でおすすめの本を紹介したハガキをだしてみよう、という取り組みです。
まず、必ず一人1枚はお手紙をもらうために、先生方が差出人と受取人を決めます。
そして、受取人の人に向けておすすめの本を紹介したはがきを書いて、図書館内に設置した簡易ポストに入れます(本当にただ段ボールに赤い画用紙を貼って、ポストに見立てたものです)
それを図書委員さんが、郵便配達員さながらに仕分けをして受取人に渡します。
受け取った人は図書室で実際におすすめの本を読んで返事を書きます。
また返事を差出人の所にもっていきます。
はがきを受け取ると「先生、ハガキが来たからお手紙書くんだ、本の感想を書くんだ~」といいながら、おすすめの本を探して借りていく子どもたちが多かったです。
学校でも色んな取り決めをして実践しています。学校のブログや学校司書さんのブログを読むと、創意工夫しながら取り組んでいるのがよく分かります。
その⑥ 読書冊数で絵を完成させよう!
これは、読書パズルと似かよっているのですが、小さいます目をぬっていくとどんなドッド絵が現れるのか楽しみな読書イベントです。
まず、ドット絵でキャラクターの下書きをします。
図案はクロスステッチの本やネットを参考にしながら、決めていきます。
なぜクロスステッチの図案なのかというと、図案がドットで表示されているからです。
このキャラクターが良いという図案が見つかったら模造紙のます目を図案のます目通りに印をつけていきます。
図案通りに書き上げた模造紙を掲示板に張り付けて、イベントの案内をします。
児童、生徒に参加してもらうときには、本を借りた冊数だけ、指定したマス目に指定した色をマス目に色をぬってもらいます。
冊数が増えるごとにキャラクターが出てくるので、どんなキャラクターなのか想像している子もいました。
ます目にあわせて各色の画用紙を切っておくというのもありですし、付箋を使ってもいいですね。
その⑦ しおりづくり
これは定番の読書イベントだと自分では思っています。
用意するのはしおり用に切った色画用紙に、マスキングテープ、雑誌や絵本の帯の切りぬき、はさみ、のり、色鉛筆などです。
しおりを作りたい人は、しおり作成リストに名前を書いてもらい、当日は色鉛筆やのり、ハサミを持参してもらいます。
そして思い思いに画用紙を切ったり、切り抜きを貼り付けたり、組み合わせたりしてオリジナルあふれるしおりができあがります。1枚作るのにもけっこう時間をとるため、最初はひとり1枚だけ作ることができる形にしていましたが、交換したりご家族にあげたりするために、2枚目、3枚目とつくるしおりが増えていきました。
できあがったしおりは、名前を書いてもらったあとに1度回収し、ラミネートしてから本人に渡すように担任の先生に頼んでいました。
その⑧ かんたんシールづくり
この「かんたんシールづくり」はカタログや雑誌の中から、可愛いものやきれいなもの、動物などの紙を切り取って集めていた時に、ふと
「これでシールつくれないかな?かんたんなやつ」と頭の中に思い浮かんだのはブックコートの中途半端な余りを見たときでした。
そして、小さな雑誌の切り抜きを、ブックコートを半分ほどあけた中に、切り抜きをはさんでまたブックコートをはめなおす。
すると、ブックコートをはがした部分がシールみたいになって、実際に貼れるのです。
こうすると、いろんな簡易シールが出来上がるのでイベントや景品にもにもつかえます。
今年(R7)の読書月間イベントはこれやりました!
今年から勤務校では運動会を10月に行うことになりまして。
それじゃあ読書月間と被るよね?9月にうつす?という内容の職員会議を通過して9月に変更になりました。
読書イベント何しようかなと考えたのですが、子どもたちが「あのイベントやりたい!」というリクエストがあったので、それをやることにしました。
今年の読書月間イベント① しおりコンテスト
去年、「オリジナルのしおりを作ってしおりコンテストに参加しよう!」というキャッチフレーズで行ったしおりコンテスト。
白色のしおり用紙に、絵や標語を自由に書いてきてもらい、それを集めたものを投票でどのしおりがよくできているかを子どもたちに決めてもらいました。
気を付けたことは、このしおりは投票した後で、もし、このしおりが欲しい子がいた場合、コピーしてあげてもいいかな?と聞いて、しおりを描いた子の了承を得てからしおりを掲示したことです。
応募して集まったしおりは模造紙で貼り付けて、図書館の廊下に掲示。
子どもたちは自分の作品やお友達のしおりを喜んで見て楽しそうに投票していました。
そして1番に選ばれたしおりは、お昼の放送で図書委員に結果発表してもらいました。それとは別に、もし「このしおりが欲しい」というしおりがあったら教えてね、と呼びかけてもらいました。
そしたら、「このしおりがいい!」「私は9番のしおりがほしい!」と希望者が多かったため、コピーしたものを配布しました。
今年も同じようにするのですが、応募数が去年より多い💦結果が楽しみです。
読書月間イベント② 毎日3冊貸出と、普段貸出しない本を1冊だけ貸出
これは、うちの学校では図鑑類が「館内」のシールが貼ってあり、普段は貸し出しをしていません。
そこで、読書月間の間だけ「館内」シールの本も貸出可能にしてみました。
すると低学年男子が図鑑を借りる借りる。恐竜に絶滅動物、固有種に魚に鳥にとまあ図鑑を持ってくる!!けっこう好感触でした。
読書月間イベント③ 昼休み限定くじ引き
月間中のもう一つのイベントは昼休み限定のくじ引き。「昼休みに本を借りた人は1回だけくじ引きができます」と案内もたてました。
15本中、あたりを3個設定。きちんと本の貸出をパソコンでチェックしてからくじびきを行いました。
これもまた盛り上がりをみせてくれました。はずれの時はまた明日チャレンジしてみようと声をかえ。当たった子にはプラスワンチケットをプレゼントしています!
この中でまねできそうなものがあった時は、ぜひやってみてください!