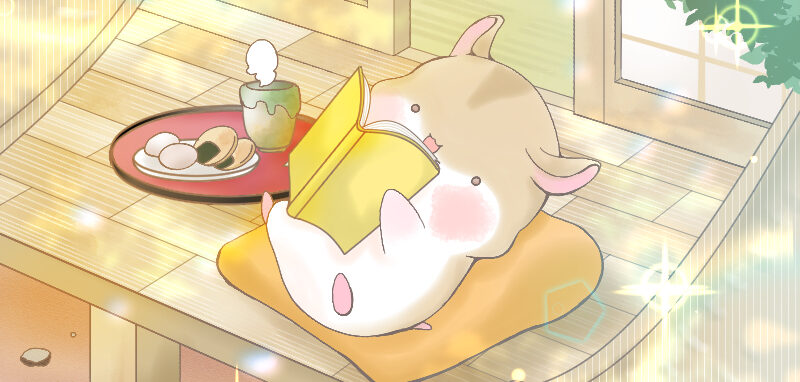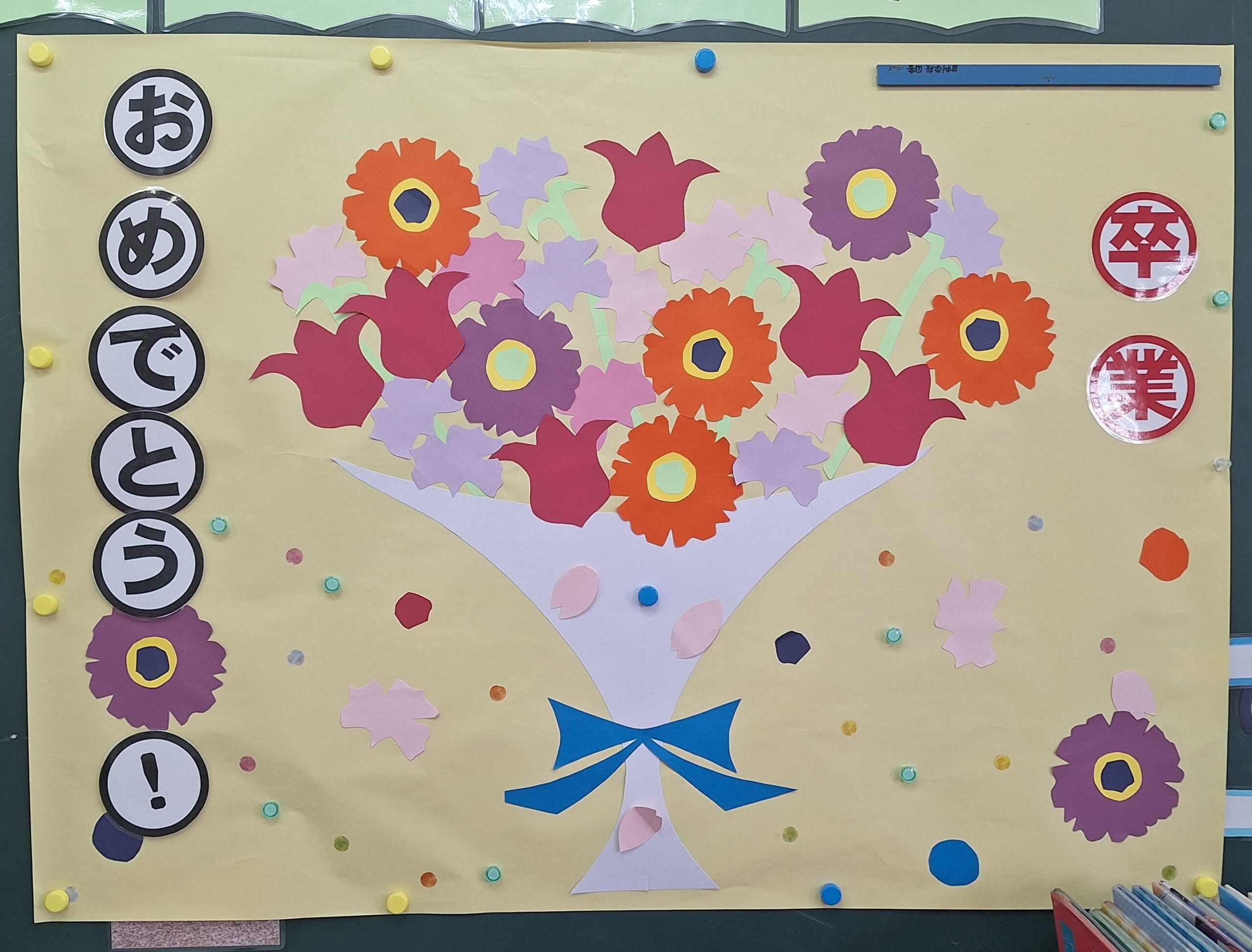こんにちは。ほんのダイアリー管理人の本野まおです。
4月は1年生にとってはじめてのことだらけ。学校図書館でもおなじことが言えます。そこで初めて利用する1年生や先生方、在校生にむけて図書館オリエンテーションを行う学校がほどんどではないでしょうか?
今回は、私の図書館オリエンテーションの流れと「図書館テスト」について説明していきます。
図書館オリエンテーションってなに?目的とねらいをおさらい
そもそもオリエンテーションとは?
オリエンテーションは、新しい環境に慣れるための説明会や研修を指します。図書館の場合、サービスの使い方や利用規則を説明し、図書館に親しんでもらうことを目的にしています。
毎年4月から5月にかけて図書館オリエンテーションをするのですが、入学したばかりの1年生や新しく赴任してきた先生方はもちろん、毎年利用している児童や先生方にも使い方のおさらいをしています。
小学校図書館でのオリエンテーションの目的
- 図書館の使い方を理解する(基本的なことから学年別に教える)
- 図書館の機能を知る(読書センター・学習センター・気分転換の場など機能はいろいろ)
- 図書館を近くに感じてもらう(本を読むだけにこだわらず、話しやすい、ふらっと立ち寄れる雰囲気を作るなど)
「図書館とは~」と単に説明するのではなく、わかりやすく、興味を持ってもらうような小道具があれば、すすめやすいです。
説明だけだと、ほんと、寝ちゃう子が出てくるんで💦ひきつける工夫って大事です。
オリエンテーションの基本的な流れと進め方
学校の実態や学年構成によってオリエンテーションの進め方はさまざまです。学専の先生と日程を決め、進行方法を計画します。
私の場合は、年度によって「全学年一括」、または「学年別」のパターンで実施しています。
実際の準備~進行
資料の作成
1・2年生用、3〜6年生用の2パターンに分けて資料を作成。それに合わせて、読み聞かせやクイズ、読書目標等も準備します。
特に兼務でされている場合は、「全学年一緒にお願いします!」と無茶ぶりを出されたりすることがあるので、児童たちが一斉に取り組めるようなクイズなどを準備します。本当は学年ごとがいいんですけどね。こればっかりは学校の、いや先生方の授業の関係もありますからね。難しいです。
実際の進行プログラム
- あいさつ・この時間のねらいの説明
- 館内ツアーと分類の説明
- 貸出・返却のデモを実演
- マナーや利用時間の確認
- 時間があれば読み聞かせやブックトーク
- Q&A、図書館イベントの案内
低学年向け「としょかんへようこそ」と「〇×クイズ」
1年生は学校図書館をはじめて利用するので、まずは短い本の読み聞かせから入ることがふえました。読み聞かせする本は図書館のマナーや決まりをまとめた本や紙芝居を読みます。
次に、「図書館にはこんな本があります。今から先生と一緒に本棚を探検しましょう!」と呼びかけて、一緒に「どこにどんな本があるか」を本を手に取ってもらいながら説明していきます。だいたい10分をめどに説明しています。
そして、貸出の決まり、マナーの説明をしてから1冊絵本を探してもらって貸し出しを貸し出しをする。というのがここ数年の流れになってます。
2年生の場合は、図書館のきまりをふりかえる目的でクイズをします。
1年間やってきたことはちゃんと覚えているかな?きちんと約束を守れているかな?と話しながらクイズに挑戦。
「借りた本は何日まで借りることができる?」 「本を借りるときには何て言ってから借りますか?」
「本を返すときはどこにいれてもOK?」など、マナーや決まりのクイズを出して自分たちの利用を振り返ってもらいます。この振り返りが大事です。間違って覚えていたりする項目もあるので、しっかりと教え込みます。
中学年・高学年向け「図書館のきまりテスト」の導入
3年生から6年生までは毎年同じような内容を聞いているので、説明を聞いてない、手遊びをしているなど目に余る行動が多い(泣)
そんな状態をなんとかしたい。けどどうしようかな。と考えていた時にふと
「あ、テストしてみたらいいんだ!」(ぬきうちで)とひらめきまして。簡単な「図書館のきまりテスト」を作りました。
テストは簡易な内容で、貸出・返却、利用時間や分類番号、マナーなどを問題にし、グループ模式で実施。
オリエンテーションの時に、テストのことは言わず「ちゃんと人の話は聞くんだぞ。今から分類について話すからね~。あとでやってもらうことがあるからね」と話してから分類の説明をしました。
そのあとで、「ちゃんと先生の説明聞いたかな?」と子どもたちに聞いてからお待ちかねの図書館きまりテストの登場!
子どもたちの「えっ?」 「テストすんの?」 「どんな問題出されんの?」という素の反応を見てテストのやりがいがあるなとひそかにほくそ笑んだ私です。
テストは10分間ほどで、結果をもとに説明やパネルの見直しへと繰り返しをしました。
実際の反応と効果
- 三年生:字の読みに苦戦し、進まず
- 四年生:分類でつまづく
- 五年生:日頃の意識の差で前半はすらすら
- 六年生:時間が足りず前半のみ
でも、これを機に分類パネルの触れ方や表示の方法を見直すきっかけにもなりました。
テスト後の学習でみえた変化
- 4年生:ポプラディアの文献検索で、分類番号を標記をもとにたどるように
- 5年生:調べ学習で分類ラベルや表示を正しく理解していた
「聞く」から「やってみる」へ。これだけでも子どもたちの意識や行動に変化があることを実感しました。
まとめ:図書館オリエンテーションは「体験型」で変わる
この一年間、図書館オリエンテーションの方法を見直し、実際に子どもたちの反応や行動を通じて「やらせる」より「自分たちでやる」方向に気づきました。
これからも、学年別の特性や意識を意識しながら、体験型の図書館演習を持続していきたいと思います。